
笑いと健康をテーマに、いかに笑いが素晴らしいかをお伝えしていきたいと思います。
「笑い」の健康への良い効果については、様々な研究でその効果が認められてます。「笑い」と健康をテーマに研究がスタートしたのは、1976年、アメリカのジャーナリストのノーマン・カズンズの闘病記。
ノーマンは「笑う」ことで自力で難病を克服したと公表した。この出来事で、「笑い」と健康の医学的な側面からの研究が幕を切りました。笑いで、免疫力が向上する。また、痛み、ストレスを感じにくくなるなどの研究報告が出てくるようになりました。現在は、「笑い」を遺伝子レベルで、健康への効果を研究もされています。
笑うと、気分が良くなったり、場の雰囲気を良い方向へ変えることもできるなど、健康に良いというのは、論文などを見なくても、肌感覚でわかりますね!積極的に「笑い」、「笑う」、「笑える」の三段活用で、健康生活を維持しましょう!
昨今の「お笑い」ブームも頷けます。
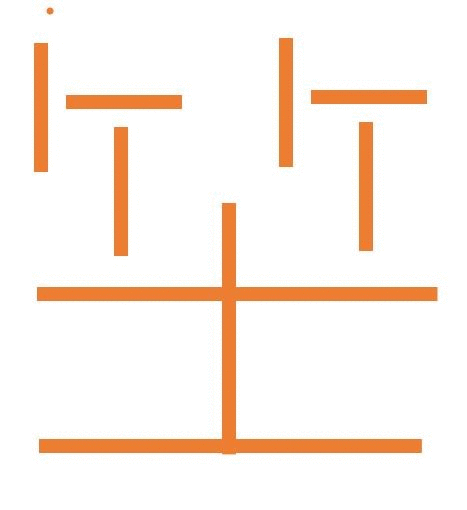
さて、笑いが健康に与える良い結果が、色々と報告されております。
実例を挙げていきたいと思います。
日本経済新聞オンライン版に記載されていたデータを元にしています。
非常に興味深い「笑い」の実験があります。
この実験に参加したのは、年齢層が中高年の糖尿病の患者さん19人。
実験の内容は以下です。
1日目と2日目の2日間に渡って実験します。2日間ともに、約500kcalの食事を摂った後、異なった内容のことをしてもらうというものです。
1日目:糖尿病についての単調な講義を受ける
2日目には吉本興業の芸人による漫才を鑑賞して大笑いした。そして、いずれの日も食事から2時間後に採血をして、血糖値がどのくらい上がったかを調べた。その結果は―。講義を聞いた日の食後血糖値は平均で123mg/dL上がったのに対し、漫才を鑑賞した日は77mg/dLの上昇だった。つまり、漫才で爆笑した日は講義を聞いた日に比べ、食後血糖値の上昇が46mg/dLも抑えられていたのだ。
“笑い”は、糖尿病患者の食後の血糖値上昇を抑制したのだ!!

(出典:Diabetes Care.2003;26:1651-1652. Personalized Medicine Universe.2012;1: 2-6)
NPO法人のプロジェクトaH(アッハ)は、関西大学名誉教授の木村洋二の「笑い」の研究を引継ぎ、2010年に発足しました。
このプロジェクトaH(アッハ)は、歩数計のように笑いの回数や頻度を簡単に計測し、健康状態、人間関係の判定に活用しようというもの。
こんな「笑い声測定システム」を、NPO法人のプロジェクトaH(アッハ)が開発した。
スマートフォン、タブレット端末に専用のソフトウエアをダウンロードし、市販の咽頭マイクを接続して利用。これまでの腹部に電極を貼付けて、笑いを定量的に測定する研究を続けてきたが、配線が必要なうえ一度に8人までしか計測できなかった。
新しいシステムは装着が簡単で約50人の笑いを同時に計測できる。
「笑い」が免疫力を高めるという研究があり、このシステムを使えば笑いの定量的な値を用いて検証できるようになる。友人、会社の同僚、知人との相性を判定する笑いによる測定法、テレビ番組の面白さを表す指標作りなどの応用が考えられるという。
「笑い」に定量という概念が入れば、本当に、本当に面白いですね!
ただ、これは永遠のテーマなので、本当に実現できるか?実用性あるのか?
これからに注目したいですね!!!
日本笑い学会というものがあり、1994年7月9日に設立された大阪に事務局があります。
日本お笑い学会は、「笑いとユーモア」に関する総合的な研究を行ない、笑いに対する認識をy深め、笑いの文化的発展に寄与することを目的とする。
「笑いとユーモア」に関する研究は、これまでは、哲学、心理学、文芸学、人類学、医学などの分野で専門的に行なわれてきたが、本学会は、各専門分野を超えて交流を深め、笑いの総合的研究を目指す。
[出典:日本笑い学会]
学会の代表者は、森下伸也氏(関西大学教授)で、関西大学名誉教授の木村洋二氏の教え子のようです。
学会の構成員
また、学会の構成員は職業を問わず、笑いに強い関心を抱いている人であれば、誰でも学会に参加できることとしている。本学会は、大学教員、医師、歯科医、看護師、高校教員、小学校教員、公務員、アナウンサー、テレビプロデューサー、新聞記者、評論家、作家、お笑いタレント、僧侶、弁護士、カウンセラー、会社役員、会社員、主婦、学生など様々な職種の会員によって構成されている。本学会は、開かれた「市民参加型学会」と称している。現在の会員は、1,000名を超えている模様。
学会の組織と運営
総会で選ばれた理事・監事・顧問46名で「理事会」を構成し、毎月1回理事会が開催されて、学会の運営にあたっている。学会の組織は、北は北海道から南は九州まで及んでおり、地域によっては支部を構成して、支部独自の活動を行なっている。2016年12月現在、全国に16支部が活動している。
学会の研究活動
1. 総会・研究発表会(年1回7月に開催)
大阪と支部のホーム&アウェイ方式で、隔年に開催している。
→ 過去の総会・研究発表会の記録はこちらから
2. 研究会
「笑いの理論」「笑いと地域」「笑いと芸術・芸能」「笑いと健康」「笑いとコミュニケーション」の五つの部会に分かれて、各部会が年1回ペースで研究会を開催している。
3. オープン講座
学会員が自由に自分の研究活動を発表できる。学会が主催し、月1回日曜日に開催している。
→ 最新のオープン講座はこちら
→ 過去のオープン講座一覧はこちら
4. 機関誌『笑い学研究』(年1回、総会の際に発行)
5. 学会ニュースレター『日本笑い学会新聞』(隔月に発行)
6. 学会メールマガジン(月1回発行)
→ ご登録はこちらから!
7. 他団体主催の笑いに関する催しへの協賛、講演会への講師派遣などの交流活動
ラフターヨガジャパンとは??
ラフターヨガ(笑いヨガ)のさらなる普及を通して、日本の明るい社会の創出に寄与していく団体です。
また、ラフターヨガとは以下のようなものです。
① |
「ラフターヨガ(笑いヨガ)」は笑いと深呼吸を組み合わせた健康体操。 |
|---|---|
② |
笑うことで多くの酸素を自然に体に取り入れ、心身共にすっきり元気に。 |
③ |
誰でもでき、冗談、ユーモア、コメディーに頼らない「ただ笑うだけ」 |
④ |
ラフタークラブでは思う存分に笑える、安心安全な場を提供しています。 |
ラフターヨガの効用
ラフターヨガ(笑い)を通じて、酸素が主な臓器に充分に届くことで、身体も心もエネルギー・パワーに満ち溢れた状態になります。また、ストレスのレベルが75%以上も減少、ストレス軽減が実感できます。
痛みを抑える物質のエンドルフィンのレベルが上がるので、気分が良くなり、様々な痛みが軽減されます。自信の高まり、コミュニケーションスキル、創造性も高まります。血圧低下や脈拍も低下し、リラクゼーションの効果があります。そのことにより、慢性的なうつが軽減されたという声も寄せられています。ストレスが原因で、低下している免疫系・消化器系・生殖系状態が改善されます。リンパの循環が活性化、血行が良くなります。
ラフターヨガを行うことで、心身共に元気になることが医学的にも実証されています。
このようなすばらしい効果が期待できるラフターヨガを全国のラフタークラブで体験することができます。
また、忙しい方でも、これから紹介する動画を観て、自分でもできます。
では、早速、ラフターヨガとは、どんなものかを動画を観て下さい。
海外のラフターヨガ
カリフォルニアのビーチでのラフターヨガです。
挨拶ラフターヨガ
エクササイズの基本、挨拶ラフターです。インドの挨拶、ナマステをイメージして手と手を合わせて笑うエクササイズです。
大当たりラフター
宝くじにあたったことをイメージしながら、大喜びしながら笑うエクササイズです。
